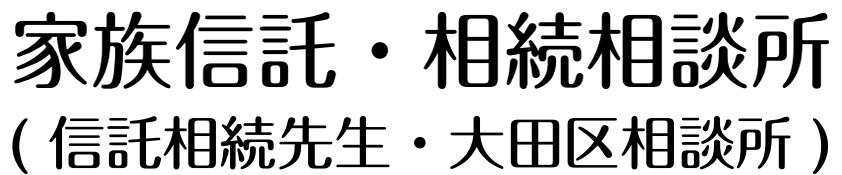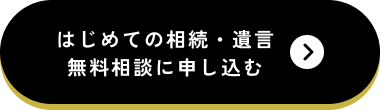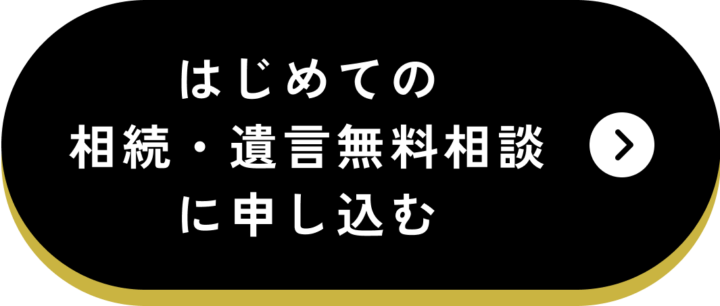相続税申告が必要なケースとは?基礎控除額の考え方と申告期限・手続きのポイント
- 公開日:
- 更新日:
高齢の親を持つ50代の子世代に向けて、相続税申告が必要になる条件や基礎控除額の仕組み、申告期限と申告までの一連の手続きについて、専門的な内容をできるだけ平易に解説します。大田区のような都市部では不動産価値が高く、「うちは普通の家庭だから相続税は関係ない」と思っていても実は申告が必要なケースがあり得ます。相続税の申告が必要か迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
相続税申告が必要となるケース(申告義務の有無)
相続が発生したとき、まず確認すべきは「相続税の申告が必要かどうか」です。 相続税の申告義務が生じるか否かは、遺産の総額が基礎控除額(一定の非課税枠)を超えるかどうかで決まります。基礎控除額以内の遺産しかない場合には相続税は一切かからず申告も不要ですが、遺産総額が基礎控除額を1円でも超える場合には、たとえ最終的な税額がゼロになるケースでも原則として申告書を提出しなければなりません。
基礎控除額の計算方法と「非課税枠」の仕組み
相続税の基礎控除額とは、各相続に共通で認められる非課税枠のことです。現行の基礎控除額は次の計算式で求めます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が1人なら基礎控除額は3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円というように、相続人の人数に応じて非課税で遺せる金額が増加します。遺産総額(プラスの財産から借金・葬儀費用等を引いた正味の遺産額)がこの基礎控除額以内で収まれば相続税はかからず申告も不要です。
注意: 基礎控除額の算定に使う「法定相続人の数」には、相続放棄をした人や既に死亡して代襲相続が発生している場合の代襲相続人も含めてカウントします。正確な法定相続人の数を把握し、ご自身のケースの基礎控除額をまず計算してみましょう。
申告が必要となる具体例と配偶者控除等の特例
基礎控除額を超える遺産がある場合には原則申告が必要ですが、中には「税金が出ないなら申告しなくてもいいのでは?」と誤解されるケースがあります。たとえば被相続人(亡くなった方)の配偶者が全財産を相続した場合、配偶者には「1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税」という大きな配偶者控除(配偶者に対する税額軽減)が適用でき、結果的に相続税額がゼロになることも多いです。しかし、配偶者控除などの特例によって税金がゼロになる場合でも、いったん遺産総額が基礎控除額を超えていれば相続税申告は必要です。相続税の申告書を提出して初めて配偶者控除等の適用が認められる仕組みですので、「税金がかからないから申告しなくて良い」というものではありません。
同様に、生命保険金の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円が非課税)や障害者控除、未成年者控除、小規模宅地特例といった各種の控除・特例を使って最終的な税額がゼロになるケースでも、一度でも遺産総額が基礎控除額を超えた場合は申告義務が生じます。専門家の立場から強調すると、税金が発生しない場合でも「相続税の申告が必要かどうか」の判断は油断できません。 基礎控除額や適用可能な控除を総合的に見て、少しでも課税ラインを超える可能性があれば期限内に申告書を提出するのが安全です。特に配偶者が相続人に含まれるケースでは「税金ゼロでも申告要」という点に注意しましょう。
大田区のケース:身近な例で考える申告要否
東京・大田区のようなエリアでは、平均的な自宅の土地と建物だけでも評価額が数千万円になることがあります。
例えば、大田区在住のAさん(子1人相続)のケースでは、自宅不動産と預貯金を合わせた遺産総額が5,000万円でした。一見それほど裕福ではないように思えても、法定相続人1人の基礎控除3,600万円を超えるため相続税の申告が必要です。最終的には配偶者控除が使えず子が全て相続するケースだったため約5万円の相続税が発生しましたが、仮に税額がゼロになった場合でも申告書の提出は欠かせません。このように都市部では「普通の資産規模」と思っていても申告義務ラインを超えているケースが珍しくありません。 心当たりがある方は早めに専門家に相談するなど準備を進めましょう。
相続税の申告期限と早めの準備の重要性
相続税の申告・納税期限は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内と法律で定められています。例えば、1月15日にお亡くなりになった場合、その年の11月15日が申告期限です。10か月という期間は一見長いようですが、遺産整理や相続人間の協議に時間を要するためあっという間に過ぎてしまいます。特に不動産の評価に時間がかかったり、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)に手間取ったりするケースでは、想像以上に時間が不足しがちです。
税理士の実務経験から言えば、申告期限まで十分に時間があるうちから動き出すことが肝心です。 相続開始後は、戸籍収集に始まり財産調査・評価、遺産分割の協議、申告書の作成とやるべきことが山ほどあります。6か月ほど経過すると、税務署から「相続税申告のお知らせ」や「お尋ね」といった文書が届くこともあります(「期限が近いが申告漏れはないか?」という確認のお知らせ)。こうした通知が来る頃には残り4か月しかありません。大田区であれば管轄の税務署(例えば蒲田税務署など)も期限間際は相談者で混雑しますので、時間的に余裕を持って準備を進めましょう。
もし10か月以内の申告が物理的に難しい場合でも、何も手続きをしないまま期限を過ぎるのは厳禁です。分割協議がまとまらない場合は、とりあえず法定相続分どおりに各人が相続したものとして申告・納税し、後日分割内容が確定した段階で修正申告することも可能です。納税資金が足りない場合も、期限内に申告書だけは提出したうえで延納(分割納付)や物納(不動産や有価証券など現物で納付)の申請を検討しましょう。延納を認めてもらうにはいくつか条件がありますが、申告書と同時に所定の申請書を出すことが必要です(申告期限までに延納申請を行います)。物納も10か月以内に申請すれば利用可能ですが、不動産でもどんな物件でもよいわけではなく換金性の低い土地(貸宅地など)や国債など一部の資産に限られるため注意が必要です。いずれにせよ、期限を過ぎて無申告となってしまうと延滞税や無申告加算税といったペナルティが課され、本来使えたはずの特例が認められなくなるリスクもあります。そうならないためにも、早め早めの準備で期限内申告を確実に行いましょう。
相続税申告までの基本的な手続きの流れ
相続税の申告を自分で進める場合、どのような段取りで進めればよいのでしょうか。ここでは専門家に依頼しない場合のおおまかな手続きの流れを確認します(専門家に依頼する場合でも基本的な工程は同じです)。
相続人の確定と財産目録の作成
まず相続人が誰なのかを戸籍で調査・確定し、被相続人が残した財産の全体像を把握します。現金・預貯金、株式・投資信託などの有価証券、不動産(土地・建物)、車、貴金属・骨董品などプラスの財産を漏れなく洗い出し、一覧表(財産目録)にまとめます。同時に、借入金残高や未払医療費、未納の税金、葬儀費用などマイナスの財産も忘れずリストアップします。大田区のように不動産の多い方は、不動産の登記簿や固定資産税評価証明書を取得しておくと評価額の算定に役立ちます。また、生前3年以内(※2024年以降は原則7年以内)に被相続人から贈与を受けていた財産や、相続時精算課税制度で生前贈与された財産がある場合は、それらも相続財産に含めて計算する点に注意しましょう。遺言書の有無もこの段階で確認します(遺言書が見つかった場合、記載内容に沿って分割方法を検討します)。
各財産の評価額を算出し課税額を試算
財産目録ができたら、次に各資産の相続税評価額を計算します。預貯金や現金は残高そのままが評価額ですが、不動産は路線価や固定資産税評価額にもとづき評価し直す必要があります。株式や投資信託は相続発生時の終値や基準価額など所定の方法で評価します。すべてのプラスの財産評価額の合計からマイナスの財産を差し引き、正味の遺産額(課税遺産総額)を算出しましょう。その上で前述の基礎控除額と比較します。正味遺産額が基礎控除額以内であれば申告・納税の必要はありません。**超えている場合には課税対象となる可能性が高いので、次に相続税額の概算を行います。相続税の税率は累進課税(課税額が多いほど税率も高くなる)で最低10%から最高55%まで段階的に定められています。ただし実際の計算方法は少し複雑で、まず課税遺産総額を法定相続分どおりに各相続人に分けたと仮定し、それぞれに課税して税額を出し、最後に各自の取得分に応じ按分し直す方式が採られています。自力で正確に算出するのは難しいため、国税庁のホームページにある「相続税申告書作成コーナー」**や民間の相続税シミュレーションソフトを活用しておおまかな税額を計算するとよいでしょう。また配偶者が相続人にいる場合は先述の配偶者控除(最大1億6,000万円まで非課税)を適用すると税額が大きく減少しますし、相続人に未成年者や障害者がいればそれぞれ控除額(未成年者控除・障害者控除)を差し引けます。利用できる特例・控除を反映して最終的な税負担を試算しておけば、後の申告書作成がスムーズになります。
相続税申告書の作成と必要書類の準備
税額の試算までできたら、いよいよ正式な申告書類を作成します。相続税の申告書(第1表ほか各付表様式)は国税庁ウェブサイトからダウンロードするか、税務署で入手可能です。まず申告書一式を準備し、手引きに沿って被相続人や相続人の情報、各人の取得財産の内容と評価額、適用する特例の有無、計算した税額など所定の事項を漏れなく記入します。相続税申告書は第1表から第15表まであり、適用する特例ごとに添付の計算書も必要になるため、不慣れな方にとっては相当なページ数になります。加えて、申告書には多くの添付書類が必要です。典型的な必要書類の例は以下のとおりです。
- 被相続人および相続人全員の戸籍謄本類(被相続人については出生から死亡までの連続した戸籍、除籍謄本など一式。相続人については現在の戸籍謄本)
- 被相続人の住民票除票(死亡により除票となった住民票。最終住所地の市区町村で取得)
- 相続人全員の住民票(相続人の現在住所を証明)
- 遺産に関する資料:預貯金通帳の写し・残高証明書、有価証券の残高証明書や評価計算明細、不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書、生命保険金の支払通知書 等
- 債務や葬式費用を証明する書類:借入金残高証明書、医療費や葬儀費用の領収書 等
- 遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を決めた合意書。もし作成できていれば提出) など
これら必要書類をすべて揃え、相続税申告書に添付して提出します。書類が一つでも欠けると受理してもらえず、後日補完提出が必要になりますので注意しましょう。
税務署への申告書提出と納税
作成した申告書と添付書類の一式が揃ったら、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。提出方法は税務署窓口へ持参するか郵送でも可能です(近年では国税庁の電子申告システムe-Taxでオンライン提出する方法もあります)。大田区の場合は蒲田税務署または大森税務署が窓口となります。提出期限は繰り返しになりますが死亡から10か月以内厳守です。 期限日までに申告書の提出と算出した相続税額の納税を完了しなければなりません。納税方法は現金納付が基本ですが、金融機関振込や振替納税、e-Tax経由の納付も可能です。なお、前述した延納(分割払い)を利用したい場合は申告書と同時に延納申請書を提出し、担保の提供など所定の要件を満たす必要があります。延納が認められると5年から最長20年の分割払いが可能です。また物納(現物納付)の申請も同様に期限内に行います。
以上が大まかな手続きの流れです。自分で申告する場合は、不慣れな手続きに戸惑う場面も多いですが、ひとつひとつ着実に進めることが大切です。 特に添付書類の漏れや申告書記入ミスがあると後から修正・補足対応に追われ、せっかく準備したのに受理されない…といった事態にもなりかねません。提出前に書類一式をよく確認し、心配な点は税務署や専門家に問い合わせてでもクリアにしておきましょう。
専門家への相談も検討を
相続税申告は一度きりの大事な手続きであり、ミスなく完了させることが何より重要です。大田区家族信託・相続の相談所のような専門窓口や税理士事務所では、申告手続きに関する個別相談を受け付けています。税理士の立場から言えば、相続税の申告は書類作成から税額計算まで専門知識を要する作業ですので、不安がある場合は早めにプロに相談するのがおすすめです。 実際にご自身で対応された方の中には、「後から間違いに気づいて修正申告になった」「特例を適用し忘れて余計な税金を払ってしまった」というケースもあります。専門家に依頼すれば費用はかかりますが、正確かつ有利に申告できる安心感と時間労力の節約につながります。特にお仕事で忙しい方や遠方にお住まいの相続人にとって、プロの支援は心強いものです。
税務署への提出が完了したらひと安心ですが、相続税の場合は申告後に税務調査(税務署からの照会や確認)が入る可能性もあります。 提出書類に不備や疑問点がなければ調査に選ばれる可能性は高くありませんが、それでも不安な場合は専門家にチェックしてもらうとよいでしょう。万一、申告後に税務署から問い合わせや調査があった場合でも、税理士に依頼していれば適切に対処策を講じてくれます。相続税の申告は「これで完了」というゴールが見えづらく不安も大きい手続きですが、専門家のサポートを得ながら進めれば安心感が違います。
相続税のご相談は大田区家族信託・相続の相談所へ
相続税申告が必要なケースや基礎控除額の仕組み、申告期限と手続きの流れまで、相続税申告の基本についてご説明しました。大田区家族信託・相続の相談所では、相続税の申告や生前対策に関するご相談を初回無料で承っております。大田区にお住まいで「うちの場合は申告が必要?」「申告手続きに不安がある」と感じている方は、お気軽にお問い合わせください。税理士など専門家の立場から丁寧にアドバイスし、大切な相続手続きが円満に完了するよう親身にサポートいたします。