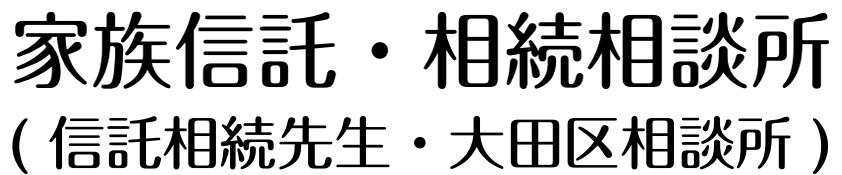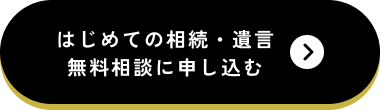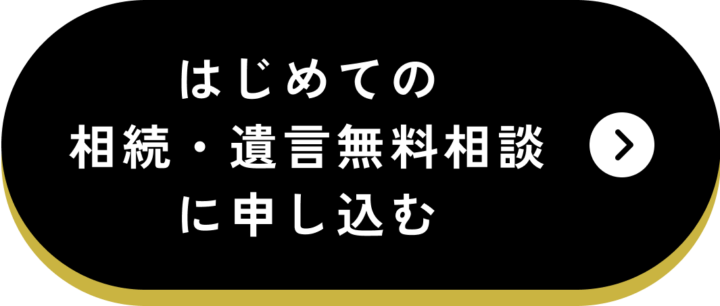生命保険・不動産を活用した相続税対策のメリットと注意点
- 公開日:
- 更新日:
相続税の負担を軽くする方法には、生命保険の活用や不動産への資産組み換えなど様々な選択肢があります。それぞれの対策には独自の仕組みやメリットがありますが、同時に注意すべきポイントも押さえておくことが大切です。ここでは、50代の子世代の方向けに、親の相続に備える主な相続税対策とその留意点を大田区の事情も踏まえてわかりやすく解説します。
生命保険を活用した相続税対策
生命保険は相続税対策としてよく活用される手段です。その理由は、生命保険金には相続税法上の非課税枠が設けられており、相続人(法定相続人)が受け取る死亡保険金の一部が非課税になるからです。さらに、契約形態を工夫することで所得税の非課税枠を利用し、結果的に相続税負担を軽減できる場合もあります。以下、生命保険を使った具体的な節税ポイントを見ていきましょう。
死亡保険金の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)の活用
被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入し、相続人が死亡保険金を受け取った場合には、「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税が非課税になる仕組みがあります。この規定を一般に「生命保険金の非課税枠」と呼びます。例えば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、最大1,500万円までの死亡保険金が相続税の課税対象から除かれます。受取人が相続人でない場合(例:孫や兄弟姉妹が受け取る場合)はこの非課税枠は使えませんので注意が必要です。
具体例
法定相続人が子ども2人の場合、非課税枠は500万円 × 2人=1,000万円となります。このケースで死亡保険金800万円を子ども達が受け取った場合、1,000万円の枠内に収まるため受け取った保険金全額が非課税になります。一方、現金で800万円を遺した場合は基礎控除枠を超えればその全額が課税対象となる可能性があります。生命保険金は受取人固有の財産として遺産分割協議の対象外で直接受け取れるため、迅速に葬儀費用や相続税の納税資金に充てられる点でも有用です。こうした理由から、生命保険は「相続発生時にすぐ現金を用意でき、かつ一定額まで非課税にできる」一石二鳥の対策として広く利用されています。
保険料の負担者を工夫して所得税非課税枠も活用
生命保険金に係る課税は、「誰が保険料を負担したか」と「誰が受取人か」によって相続税・所得税・贈与税のいずれが課税されるかが変わることをご存知でしょうか。典型的な契約では、被相続人自身が保険料を支払い、相続人が死亡保険金を受け取るため相続税が課税されます。しかし、保険料負担者と受取人を同一人物(子ども本人など)にする契約形態にすれば、死亡保険金は相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となります。
一時所得には年間50万円の特別控除があり、さらに課税対象額はその利益部分の1/2だけです。結果として、相続税課税の場合よりも低い税負担で済むケースがあります。専門家の視点: 税理士の立場から見ると、親の相続税率が高くなりそうな場合、この契約形態にして所得税課税に切り替えるとかなり税負担を抑えられることがあります。
具体例
子どもが契約者(保険料負担者)となり、親を被保険者・子ども自身を受取人とする生命保険に加入したケースを考えます。仮に子どもが支払った保険料総額が500万円、死亡保険金が1,000万円だった場合、所得税の計算上は受取額1,000万円-支払保険料500万円-特別控除50万円=450万円が一時所得となります。その1/2の225万円が課税対象となり、仮に所得税・住民税率を合計20%程度とすれば約45万円の税負担です。一方、これを相続税で課税すると、たとえば相続税率が20%の層であれば同じ1,000万円に対して200万円の税となる可能性があります。比較すると、所得税課税に切り替えたことで大幅に負担を抑えられるケースがあるわけです。
この方法では死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)は使えなくなるものの、所得税の特別控除・1/2課税を活用する形で節税効果が得られます。注意点: この契約形態では子ども自身が保険料を払い続ける必要があり、支払い負担が生じます。また契約者を途中で変更すると贈与と見なされるリスクもあるため、契約時には保険会社や税の専門家と十分に相談してください。
生命保険活用のポイントと専門家のアドバイス
生命保険を使った相続税対策を検討する際は、いくつかポイントに留意しましょう。
- 非課税枠は法定相続人が受取人の場合のみ: 既述のとおり、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)は受取人が法定相続人であることが条件です。実際の相続人ではない孫や兄弟姉妹を受取人にした場合、その人には相続税の非課税枠は使えず保険金全額が課税対象になります。受取人の設定には注意が必要です。
- 受取人の人数を活かす: 非課税枠は法定相続人の人数に依存するため、受取人を複数人に設定することで枠を増やす工夫も可能です。例えば子2人が相続人なら、保険金受取人を子2人それぞれに50%ずつ指定することで、2人分の非課税枠1,000万円をフルに活用できます。ご家庭の状況に応じて受取割合を調整し、可能な限り非課税枠を無駄なく使うとよいでしょう。
- 保険商品の選択: 生命保険には終身保険や定期保険、養老保険など様々な種類があり、保険料の払い方も一時払い・平準払いと選択肢があります。親御さんの年齢や健康状態、目的とする額によって適切な商品は異なります。高齢で加入が難しい場合や、保険料が割高になるケースもあります。専門家(保険会社担当者やファイナンシャルプランナー)に相談しながら、無理のないプランを設計しましょう。
- 契約形態の検討: 前述のように契約者・受取人を子にすることで所得税課税に切り替える方法もあります。ただし、子が保険料を負担するので子に十分な支払い能力があるか、また親が高齢で保険料が高額になりすぎないかなどの点を慎重に見極めてください。状況によっては無理に契約者変更をせず、通常の形態で非課税枠を活かす方が良い場合もあります。
大田区のような都市部では不動産資産が大きく保険だけでは十分な節税にならないケースもありますが、生命保険は「納税資金の確保」という意味でも一家に一契約は検討価値あるでしょう。節税と資金準備を兼ねた対策として、ぜひ前向きに活用を検討してください。
不動産の活用による相続税対策
現金・預金などのまま遺産を残すより、不動産を活用することで相続税評価額を下げられる場合があります。これは、不動産の相続税評価額(課税評価額)は市場価格に比べて低く算定されることが多いためです。さらに、賃貸用の不動産にすれば利用や処分に制限がかかる分、評価額が一層引き下げられる特例もあります。ここでは、現金を不動産に組み換える方法や賃貸物件・小規模宅地等の特例を活用した評価減について、具体例を交えて説明します。
評価額の低い不動産への資産組み換え(現金→不動産)
現金は額面どおり100%の評価となりますが、不動産は路線価や固定資産税評価額に基づいて評価されるため、市場価格より低い評価額になるケースが一般的です。そのため、生前に現金・預金を使って不動産を取得したり建築したりすることで、相続税の計算上の財産評価額を圧縮できる可能性があります。
具体例
現金1億円を都市部の土地に組み換えた場合、その土地の相続税評価額は「路線価 × 地積」で計算され、路線価は公示価格の80%程度が目安となります。つまり、時価1億円相当の土地でも評価額は約8,000万円に圧縮される計算です。さらに老朽化した建物を取り壊して新築不動産にするケースでも、建物評価額は建築費ベースの算定となるため、現金を投下した金額より低く評価される効果が期待できます。
ただし、不動産取得には仲介手数料や不動産取得税などコストがかかり、相続後に売却しにくい(流動性が低い)点もあるため、この後述べる注意点に留意しましょう。
賃貸物件や小規模宅地特例の活用で評価減を図る
不動産を賃貸用として活用すると、さらに相続税評価額を下げることができます。賃貸物件では、土地については「貸家建付地(かしやたてつけち)」評価が適用され、更地評価より約2割減額(評価額の約8掛け)されます。建物についても「貸家(かしや)評価」として評価額が3割減額されます(自用の建物と比べて賃借人がいる分だけ価値が低いとみなされるため)。例えば、1億円で新築した賃貸アパートの場合、土地・建物それぞれに貸家建付地・貸家の減額(土地▲20%、建物▲30%)が適用され、結果として建築後の不動産の評価額は、建築費や市場価格に比べて実質的に半分以下に抑えられる可能性があります。
また、被相続人が住んでいた自宅の土地などについては、相続人が一定の要件で引き継ぐ場合に「小規模宅地等の特例」が適用でき、最大で評価額80%減(330㎡まで)という大幅な減額措置があります。例えば、親と同居していた子が自宅土地を相続して引き続き居住する場合、この特例でその土地の評価額は2割まで下がります。都市部では土地評価が高額になりがちですが、この特例を適用できれば非常に大きな節税効果があります。
大田区のケース
大田区は住宅密集地も多く、小規模宅地特例の恩恵にあずかれるご家庭も多いでしょう。生前対策として、親と同居を続ける、もしくは亡くなった後もその家に住み続ける意思がある場合、ぜひ活用したい特例です。ただし、適用には「相続開始直前に被相続人と同居していたこと」「相続税申告期限まで保有継続すること」などの要件がありますので、事前に確認しておきましょう。
借入を活用した資産圧縮とリスク
不動産対策をさらに進める方法として、あえて借入(金)をして純資産を圧縮する方法があります。一般には、借入金を活用して前述の不動産取得や生命保険加入を行うことで、相続税評価額を下げる効果を狙います。
具体例
1億円の借入をして賃貸アパートを新築すれば、資産価値は時価1億円でも相続税評価額は先述の通り約4,200万円に圧縮され、正味の課税対象額が大幅に減少します。借入金1億円は債務控除として差し引けるため、仮に資産評価4,200万円-借入1億円=マイナス5,800万円となれば相続税は発生しません(残額は控除しきれませんが課税財産ゼロ扱い)。このように、不動産+借入の組み合わせは強力に課税価格を下げる効果があります。
しかしながら、借入を利用した対策には慎重な収支計画が不可欠です。不動産投資には空室リスクや維持費も伴いますから、借入金利と賃料収入のバランスが取れないと収支が悪化して資産を減らしてしまう可能性もあります。例えば賃貸経営が赤字になれば本末転倒で、税負担は減っても肝心の財産自体が目減りしてしまいます。このように、借入を利用した節税策には「将来の返済」というリスクが常につきまといます。親御さんが亡くなった後、残った借金を相続人が返済していけるのか、最悪の場合は不動産を手放して返済に充てることになる可能性もあります。節税のためとはいえ、残された家族に返済不能な債務を背負わせるようなことは避けねばなりません。
また、借入で購入した不動産の価値下落や収益悪化にも注意が必要です。例えば、親が築浅の賃貸マンションをローンで取得したものの、地域の賃貸需要が低迷して家賃収入が計画を下回り、ローン返済が重荷になってしまった…というケースも起こり得ます。大田区でもエリアによって賃貸需要には差がありますし、将来の不動産市況も不透明です。借入をしてまで不動産対策を行う場合は、最悪のシナリオも考慮したうえで計画を立てることが大切です。
節税策実行の際の全体的な注意点
ここまで生命保険や不動産など個別の対策について述べてきましたが、最後に相続税節税策全般に共通する注意点をまとめます。
各種対策を講じる際の注意点
ここまで見てきたように、節税効果のある対策にはそれぞれ伴うリスクやデメリットがあります。相続税対策ばかりに気を取られて本末転倒な結果とならないよう、以下の点に注意しましょう。
- 節税と資産管理のバランス: 相続税を減らすこと自体は大切ですが、家族の資産状況や生活の安定とのバランスが何より重要です。「多少相続税は発生しても、親の老後資金は現預金で十分確保しておく」「不動産は節税になるが、いざというとき売却しにくいので持ちすぎない」といったように、極端に走らずバランスを考えましょう。子世代として親に助言する場合も、「税金がもったいないから全部対策しよう!」と急かすのではなく、親御さんの安心や生活を第一に考えてあげてください。
- 専門家の活用: 生命保険や不動産、借入など複合的な対策を検討する際は、税理士・司法書士・不動産業者・FP(ファイナンシャルプランナー)など専門家の知見をフルに活用しましょう。専門家としても、それぞれの分野のプロと連携しながら総合的な提案を行うことが重要だと感じます。大田区家族信託・相続の相談所ではワンストップで各種専門家と相談できますので、ご不安な点はぜひお気軽にご相談ください。
- 最新の制度にアンテナを張る: 相続税制は時々刻々と変化しています。今回ご紹介した制度も2024年の改正で変わった点があります。今後も税制改正により有利・不利が変わる可能性がありますので、最新情報に注目しましょう。専門家に相談すれば最新動向も踏まえたアドバイスが得られます。
まとめ
生命保険や不動産の活用は相続税対策として有力ですが、メリットの裏にあるリスクやコストも踏まえて判断することが大切です。節税策はあくまで手段であり、最終目的はご家族の幸せと大切な財産の有効活用にあります。メリハリの効いた対策で、無理なく賢い資産承継を目指しましょう。
相続税のご相談は大田区家族信託・相続の相談所へ
生命保険の活用や不動産への資産組み換えによる相続税対策のメリットと注意点について解説しました。大田区家族信託・相続の相談所では、これら相続税の節税策を含め、お客様の状況に応じた最適なプランをご提案いたします。節税は大切ですが、同時にご家族の安心や資産運用の観点も見据える必要があります。大田区で相続対策をご検討中の方は、ぜひ当相談所の無料相談をご利用ください。税理士・FPなど専門家がチームで皆様の大切な財産を守るお手伝いをいたします。