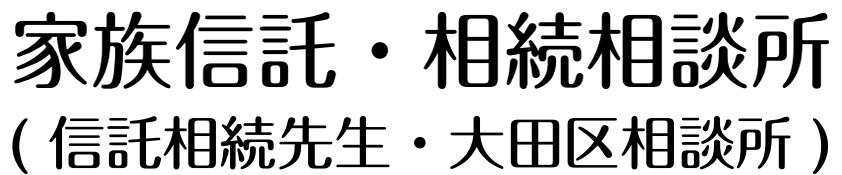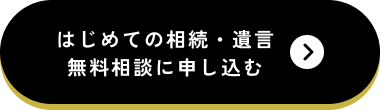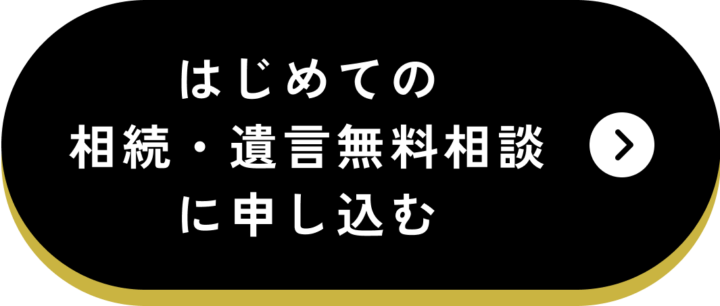生前贈与を賢く活用した相続税対策:非課税枠の上手な使い方と注意点
- 公開日:
- 更新日:
親から子や孫への生前贈与は、相続税対策として非常に有効な手段として注目されています。相続税は亡くなった時点の遺産総額に応じて課税されますが、生前のうちに財産を子や孫に移しておけば、その分だけ将来の相続財産が減り相続税の負担軽減につながるからです。特に日本の相続税制では、生前贈与に利用できる様々な非課税枠が用意されており、年間110万円まで非課税の暦年贈与や、一度に大きな額を移転できる相続時精算課税制度などを上手に活用することで効果的な対策が可能です。
本記事では、50代で親の相続を見据える読者の方に向けて、生前贈与が相続税対策に有効な理由と具体的な活用法、さらに注意すべきポイントを大田区の事例や仮想ケースも交えながらわかりやすく解説します。大切な財産を次世代に引き継ぐために今からできる工夫を確認し、賢い相続税対策にお役立てください。
生前贈与が相続税対策に有効な理由
生前に財産を移転し相続財産そのものを減らせる
生前贈与とは、その名のとおり生きている間に自分の財産を子や孫などに贈与することです。事前に財産を移しておくことで、亡くなった時点での相続財産を減らし、結果的に相続税を抑える効果があります。極端な例ですが、生前に全財産を使い切ったり譲り終えてしまえば、相続発生時には課税財産が残らないので相続税はかかりません。
もちろん現実には生活資金等もあるため全ては無理ですが、できる範囲で早め早めに財産を移していけば、最終的な相続税額が大幅に減るケースもあります。ある試算では、20年間にわたり毎年非課税枠内で配偶者と子4人に贈与し続けたところ、生前贈与を全くしない場合に比べて相続税が約1,361万円も少なくなったと報告されています。この試算は特例などもフル活用したケースと思われますが、生前贈与によって相続財産自体を減らすことができれば、それだけ納める相続税も減るという点は明らかです。
相続人の数や贈与のタイミングによる節税効果の違い
生前贈与の効果は、相続人の人数や贈与を始めるタイミングによっても変わってきます。まず相続人(贈与の受取手)が複数いる場合、それぞれに年間110万円ずつ贈与すれば合計でかなりの額を非課税で移転できます。例えば相続人が子ども2人いれば各110万円で年間計220万円、子ども3人なら年間330万円まで贈与しても贈与税はかかりません。相続人の数が多いほど、一度に移せる非課税額が増えて相続財産を効率的に目減りさせやすいということです。逆に相続人が少なければ非課税で移せる総額も限られるため、より長期間かけてコツコツ贈与していく必要があるでしょう。
また、生前贈与は早く始めるほど効果的です。高齢になってから慌てて多額の財産を贈与しても、それが死亡前3年以内(※2024年以降の贈与は段階的に7年以内へ延長)であれば相続財産に持ち戻されてしまい節税になりません。税法上、「駆け込み贈与」は相続税逃れと見做され、防止措置として一定期間内(現行3年、将来7年)の贈与は相続税計算時に加算されるルールがあります。逆に、早い時期から計画的に贈与を開始しておけば、贈与から長く経過した分は相続財産に加算されにくくなるため、相続税対策としての有効性が高まります。実際、2024年の税制改正で持ち戻し対象期間が7年に延長されることになり(2024年以降の贈与に適用)、今後はより一層「早めの贈与開始」が求められるようになっています。
仮想事例:早く始めた場合と遅れた場合の違い
Aさん(現在70歳)は、自身の財産を早めに子どもたちに渡そうと決め、60代のうちから毎年贈与を開始しました。毎年少額ずつ計画的に贈与した結果、Aさんが80代で他界した際には、その20年以上前に贈与した分は相続財産に含まれず、おかげで相続税の負担も大幅に抑えられました。
一方、Bさん(80歳)は体調を崩したのを機に、慌てて子どもに多額の贈与をしました。しかしBさんはその2年後に亡くなってしまい、亡くなる直前3年以内の贈与だったため、その贈与額は相続税の計算に加えられてしまいました。結果としてBさんの相続税額は想定より減らず、駆け込み贈与の効果がほとんどありませんでした。
この事例からも分かるように、生前贈与は思い立ったらすぐ動くことが肝心です。 元気なうちから始めたAさんはしっかり節税できましたが、遅かったBさんは間に合いませんでした。将来を見据えて早めに行動することが何よりのポイントです。
生前贈与の具体的な方法と非課税枠の活用
生前贈与を活用する際、主に考えられる方法は「暦年贈与」(毎年の110万円非課税枠を使う方法)と「相続時精算課税制度」(まとまった額を贈与する方法)の2つです。それぞれの仕組みとメリット・デメリット、注意点を押さえておきましょう。
暦年贈与の基本(年間110万円の非課税枠を活用)
暦年贈与の仕組みとメリット
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、1年間(毎年1月1日~12月31日)にもらった財産に対して課税を判断する贈与税の仕組み(暦年課税制度)のことです。暦年贈与では前述のとおり年間110万円までの贈与税の基礎控除(非課税枠)が設けられており、その範囲内なら贈与税がかかりません。この制度を利用して毎年非課税枠内で贈与を行えば、相続が発生する頃には相当額の財産を減らせる可能性があります。
暦年贈与の最大のメリットは、前述したようにコツコツと長期間にわたって財産を移転できることです。例えば、子ども一人に対して毎年110万円ずつ10年間生前贈与すれば、合計1,100万円を無税で移転できる計算になります。家族の人数が多ければ各人に110万円ずつ贈与することで、一度に数百万円規模の財産を移すことも可能です。また、暦年贈与は用途が限定されていないため、教育資金や住宅資金など特定の目的に限らず、現金でも不動産でも自由に贈与できる柔軟さがあります。贈与を受けたお金の使い道は受贈者次第なので、「子や孫に早めに財産を分けてあげたい」というシンプルな目的にかなう方法と言えるでしょう。
暦年贈与の注意点(贈与契約書・計画性など)
既に前述した内容と重なる部分もありますが、暦年贈与で非課税枠をフル活用するには以下のポイントに注意が必要です。
- 毎年継続して贈与する計画性: 暦年贈与は一度に多額を移せない代わりに、長期的に続けることで効果を発揮します。途中で中断せず、可能な限り毎年欠かさず贈与を続けることが肝心です。「今年は余裕がないからゼロ」という年を作ってしまうと、その分非課税枠を捨てることになります。無理のない範囲で継続しましょう。
- 贈与契約書の作成: 毎年の贈与については必ず贈与契約書を取り交わし、贈与者(親)・受贈者(子など)双方が署名押印して保管してください。これにより後で贈与の事実を証明しやすくなりますし、親族間の認識違いやトラブルも防げます。「あげるつもりで通帳に入れておいたが、実は名義が子になっていただけだった」などと後から揉めないよう、書面を残す習慣をつけましょう。
- 定期贈与と見なされない工夫: 前述した定期贈与の疑いを避けるため、契約書には毎年その都度の贈与であることを明記します。「今後○年間に毎年○万円ずつ贈与する」など将来分の約束を書かないよう注意してください。税務上、毎年の贈与が一括契約になっているとまとめて課税されるリスクがあるためです。一年一年独立した贈与として扱えるようにしましょう。
- 受贈者管理の徹底: 子や孫の口座に振り込んだお金は基本的に受贈者の財産です。親が引き続き管理・運用していては贈与が成立していないと判断されかねません。 贈与後のお金の管理は原則受贈者本人(未成年の場合は親権者)に任せ、親が自由に引き出したりしないようにしましょう。
結論として、相続時精算課税制度は大きな額を早く渡したいニーズには合致しますが、相続税の節約という点では慎重な検討が必要です。利用を考える際は必ず税理士等専門家にシミュレーションしてもらい、本当に得かどうか確認することをお勧めします。
生前贈与を行う際の共通の注意点
最後に、生前贈与全般に言える注意点を整理しておきます。
- 贈与税の申告漏れに注意: 暦年贈与でも相続時精算課税でも、贈与税の申告が必要な場合は必ず期限内(贈与した翌年2月1日~3月15日)に申告を行いましょう。たとえ税額がゼロでも、申告しないと特例適用の権利を失う場合があります。特に相続時精算課税は毎年の申告が重要です。申告漏れは延滞税・無申告加算税といったペナルティの対象にもなりますので注意してください。
- 記録と証拠をきちんと残す: 贈与契約書、通帳の写し、振込明細など、贈与の事実と内容を示す証拠書類はしっかり保管しましょう。相続時に税務署から「○年前に多額の預金引出しがあるが何に使ったのか?」と問われるケースがあります。その際に「この年に子に贈与しました」と即答でき、書面も提示できれば安心です。
- 家族間で情報共有する: 生前贈与は相続人間で公平性の問題が生じることもあります。特定の子にだけ多額の贈与をしている場合、他の子が事前に知らないと後で不満を持つかもしれません。将来のトラブルを避けるため、誰にどれだけ贈与するか家族である程度共有し、納得を得ながら進めることも大切です。
- 生活資金を圧迫しない: 節税のあまり、生前贈与で親御さん自身の生活資金を減らし過ぎないようにしましょう。高齢の親の生活や介護費用を十分確保しておくのは最優先事項です。専門家としても、節税と老後資金のバランスを考慮するよう常にアドバイスしています。 無理なく可能な範囲での贈与に留め、親御さんの安心を損なわないよう注意しましょう。
以上のポイントに気をつけながら、生前贈与を賢く活用してください。生前贈与は相続税対策として強力な武器ですが、制度を正しく理解し、計画的かつ適切に行うことが成功の秘訣です。必要に応じて税理士等に相談しながら、円満な資産承継を進めましょう。
相続税のご相談は大田区家族信託・相続の相談所へ
生前贈与を活用した相続税対策のメリットと注意点について、非課税枠の仕組みから具体的な贈与方法(暦年贈与・相続時精算課税制度)まで詳しく解説しました。大田区家族信託・相続の相談所では、生前贈与による相続税対策や贈与税申告に関する無料相談を承っております。「どのくらい贈与すればいいの?」「相続時精算課税を使うべき?」といった疑問にも、相続・税務の専門家が丁寧にお答えします。大切な財産を次世代に賢く引き継ぐお手伝いをいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。