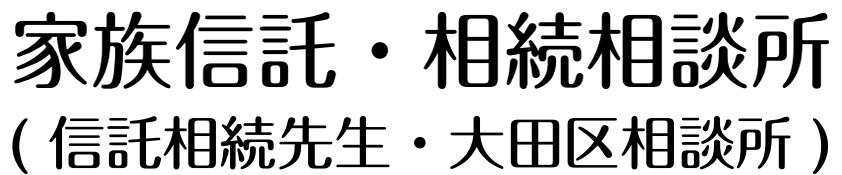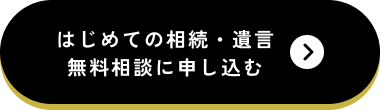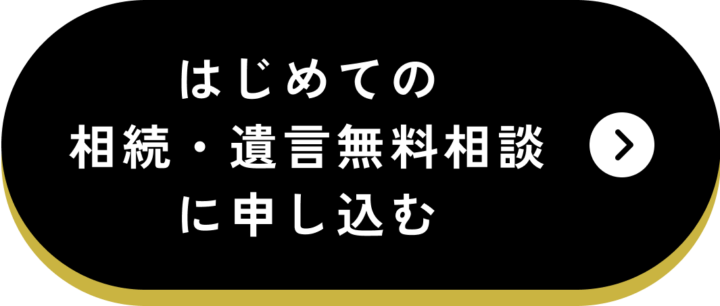相続税対策の基本と早めに始める生前対策のポイント
- 公開日:
- 更新日:
相続税対策は、高齢の親を持つ50代の子世代にとって早めに取り組みたい重要テーマです。近年の税制改正により相続税の課税対象が拡大し、大田区のような都市部にお住まいの一般的なご家庭でも相続税が無視できないものとなりつつあります。相続税の制度は2015年(平成27年)の改正で基礎控除額が大幅に引き下げられ、従来はごく一部の富裕層だけが対象だった相続税が、今では亡くなられた方全体の約1割に課税される状況です(※国税庁の統計では令和5年時点で約9.9%)。遺産が課税ラインに達すると数百万円規模の税負担が生じるため、事前の対策準備が欠かせません。
本記事では、相続税対策がなぜ必要かという理由から始めて、知っておきたい相続税の基礎知識、生前にできる具体的な節税策の種類、そして対策の第一歩となる資産把握と専門家への相談について解説します。専門的な内容もできるだけ平易にまとめていますので、「まだうちは先の話」と思わず今日からできる相続税対策の参考にしていただければ幸いです。
相続税対策が必要な理由(早めの準備の重要性)
課税対象の拡大で他人事ではなくなった相続税
かつて相続税は「資産家だけの特別な税金」というイメージがありました。しかし平成27年の税制改正で基礎控除額が縮小された結果、ごく普通の家庭でも相続税申告が必要となるケースが増加しています。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられ、例えば相続人が配偶者と子2人(法定相続人3人)なら非課税枠は4,800万円です。このため、自宅の土地建物や預貯金を合わせて4,800万円を少しでも超える遺産があると、相続税の申告・納税が必要になります。改正前は亡くなる方のうち相続税がかかるのは4%前後という時期もありましたが、現在では約1割が課税対象となっている状況です。特に都市部の不動産をお持ちのご家庭や、相続人が少なく基礎控除額が小さいケースでは、決して裕福でなくとも相続税が発生し得るので注意が必要です。
大田区の例:
例えば大田区内に時価5,000万円程度のご自宅(土地・建物)をお持ちで、他に預金1,000万円があるご家庭を考えてみましょう。相続人が配偶者と子1人(法定相続人2人)の場合、基礎控除額は4,200万円です。このケースでは遺産総額6,000万円のうち4,200万円を超える部分(1,800万円)が課税対象となり、配偶者が全額相続したとしても税額軽減後で数十万円規模の相続税負担が生じる可能性があります。こうした身近な例からも、「うちは大丈夫」と思わず早めに対策を検討することが重要だと分かります。
生前対策は「時間を味方に」:早く始めるほど効果的
相続税対策を早めに始める最大の理由は、時間をかけることで節税効果を高められる点にあります。典型的なのが後述する暦年贈与による財産移転です。毎年コツコツと110万円ずつ非課税で贈与する暦年贈与は、長年続ければ続けるほど多くの財産を無税で次世代に移せます。
例えば毎年110万円ずつ子どもに20年間贈与すれば、合計で2,200万円を非課税で移転できる計算になり、相続時にはその分財産が減っています。
一方、相続間近になって慌てて贈与しても、被相続人の死亡前3年以内(2024年以降の相続では7年以内)の贈与財産は相続税計算上持ち戻しの対象となり、結局節税になりません。いわゆる「駆け込み贈与」は税逃れと見なされ、死亡前一定期間内の贈与は相続財産に加算されるルールがあるためです。2024年の税制改正で持ち戻し期間が3年→7年に延長されたことにより、より一層早めの贈与開始が求められるようになりました。専門家としても「生前○年ルール」に抵触しないタイミングで計画的に贈与を進めることが肝心だと感じます。
また、親御さんが元気なうちに対策を講じておけば、財産状況の正確な把握や、遺産をどう分けたいかという希望を家族で十分に話し合う時間も確保できます。早期からの生前対策は相続税の節税だけでなく、将来の相続手続き円滑化や家族間のトラブル防止にもつながる点で重要と言えるでしょう。
二次相続も見据えた対策が必要
相続税対策を考える際には、一次相続(片方の親が亡くなったとき)だけでなく二次相続(残ったもう一方の親が亡くなったとき)まで見据えることが大切です。一次相続において配偶者が大半の財産を相続すれば、配偶者控除によりその時点では相続税がかからないケースが多いです。しかしその結果、残された配偶者に財産が集中すると、後の二次相続では相続人(子)が一人減り基礎控除額も減少するうえ、相続財産が前回より膨らんだ状態で課税されるためトータルの税負担が増えるおそれがあります。そこで一次相続から子世代にある程度分散して財産を渡しておくことで、二次相続時の課税を緩和できる場合があります。
例えば、専門家の視点では、一次相続時に配偶者があえて全財産を取得せず、子にも一部相続させる「相続分配の工夫」も有効な節税策として検討します。ただし配偶者の生活保障とのバランスも重要であり、節税のために配偶者が困窮する事態は避けねばなりません。このように、二次相続まで踏まえたトータルプランニングが相続税対策には求められます。
相続税の基礎知識(基礎控除額・税率の仕組み)
相続税がかかる基準
具体的な対策を述べる前に、前提となる相続税の基本的な仕組みを押さえておきましょう。まず相続税は、遺産総額(プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた正味遺産額)が前述した基礎控除額を1円でも超えると、その超えた分に対して課税される税金です。言い換えれば、遺産が基礎控除内に収まれば相続税はかかりませんが、一旦超過すると申告・納税義務が生じます。ご自身の家庭で相続税がかかりそうか判断するには、まず自分の場合の基礎控除額はいくらかを計算してみることが大切です(法定相続人の数によって変動します)。そのうえで、現在の親の財産がおおよそいくらなのか把握し、基礎控除額を超えそうかどうか検討してみましょう。
相続税の税率は一律ではなく、課税対象となる遺産額に応じた累進税率(段階的に税率が高くなる方式)が適用されます。具体的には、基礎控除後の課税遺産総額を法定相続分で仮分割し、各法定相続人ごとに以下の速算表に当てはめて税額計算します。
- 課税遺産総額~1,000万円以下部分:税率10%
- 1,000万円超~3,000万円以下部分:税率15%(控除額50万円)
- 3,000万円超~5,000万円以下部分:税率20%(控除額200万円)
- 5,000万円超~1億円以下部分:税率30%(控除額700万円)
- 1億円超~2億円以下部分:税率40%(控除額1,700万円)
- 2億円超~3億円以下部分:税率45%(控除額2,700万円)
- 3億円超~6億円以下部分:税率50%(控除額4,200万円)
- 6億円超部分:税率55%(控除額7,200万円)
各人の税額を計算したら、実際の遺産の分け方に応じて按分し直して各相続人の納付税額が決まります(この計算法は専門家でもやや複雑なため、詳細は国税庁のガイド等を参照してください)。ポイントとして、遺産が基礎控除を大きく上回る富裕層では最高税率55%が適用される厳しい税制ですが、多くの方は課税遺産総額1億円以下に収まり税率10~20%台の範囲に収まるケースが一般的です。いずれにせよ、無駄な税金を支払わなくて済むよう生前から対策を講じる意義は大きいでしょう。
なお、相続税にはこの他にも各種の非課税財産や税額控除の制度があります(例えば生命保険金の非課税枠や、配偶者が受け取る場合の税額軽減、未成年者控除・障害者控除など)。それらも活用すれば税負担を軽減できますが、これらは基本的に申告時に適用を申告する必要があるため、結局のところ「申告が必要かどうか」の判断がスタートラインになります。対策に取り掛かる前に、まずは基礎控除額や自分の家の資産規模・構成を把握しておくことが大切です。
生前にできる主な相続税対策の種類
相続税の課税ラインを超えそうだと分かった場合、具体的にどんな対策があるでしょうか。ここでは生前に講じることができる代表的な節税策をいくつかご紹介します。いずれも「時間をかけて準備するほど効果が高まる」ものばかりですので、できるものから早めに着手すると良いでしょう。
毎年110万円までの「暦年贈与」を活用する
生前贈与(暦年課税)を活用するのは相続税対策の基本中の基本です。日本の贈与税制では、1月1日から12月31日までの1年間に個人からもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税がかからない(この範囲なら贈与税の申告も不要)と定められています。この年間110万円の非課税枠を毎年コツコツ使って子や孫に財産を移しておけば、その分だけ将来の相続財産が減り、相続税の節税につながります。
例えば、毎年お年玉代わりに子と孫3人へ各110万円ずつ贈与するケース
例えば、大田区にお住まいの70代の父親が、毎年お年玉代わりに子と孫3人へ各110万円ずつ贈与したケースでは、贈与税は一切かからず毎年合計440万円を家族に移転できます。これを10年間続ければ総額4,400万円もの財産を無税で次世代に渡せる計算です。父親が他界した時点で遺産は当初より確実に減っており、その分相続税の負担も抑えられます。暦年贈与のメリットはこのように、長期間にわたって計画的に財産移転することで大きな節税効果が得られる点にあります。ご家族の人数が多ければ各人に110万円ずつ贈与することで、一度に数百万円単位の財産を非課税で移すことも可能です。
暦年贈与を行う際のポイントは、「早く開始し長期間続ける」ことに尽きます。前述のとおり、生前贈与で節税効果を得るには贈与から死亡まで一定期間(従来3年、今後7年)を空ける必要があるため、元気なうちから贈与をスタートし、「駆け込み贈与」にならないよう十分な年数をかけて進めておくことが重要です。例えば60代から贈与を始め80代まで続ければ、20年以上前の贈与分は相続財産にカウントされず済む可能性が高まります。
税理士の視点:
税理士に生前贈与の相談を受ける際には、税理士は、次のような点に注意するようアドバイスするでしょう。
毎年の贈与契約書を作成すること
贈与する際は毎回、贈与者(親)と受贈者(子・孫)との間で「○年○月○日に○円を贈与する」旨の契約書を取り交わし、双方が署名押印して保管しましょう。契約書がないと「本当にあげたのか?」と後でトラブルになる可能性がありますし、税務署からも贈与の事実を証明しづらくなります。贈与額や日付、贈与の趣旨(お祝い金・生前贈与など)を明記した簡易な書面で構いませんので、毎年忘れず作成してください。
現金の受け渡し方法にも配慮
贈与は基本的に受贈者名義の銀行口座に振り込む形で行うのが確実です。手渡しで現金を渡すと記録が残らず、後で「実は名義預金(親のお金を子名義にしていただけ)」と判断されるリスクがあります。振込明細や預金通帳の記帳を残すことで、贈与の事実が証明しやすくなります。
110万円を超えた場合は贈与税申告を忘れずに
暦年贈与では1人当たり年間110万円までが非課税ですが、万一それを超える贈与をした場合は翌年2月~3月に贈与税の申告が必要です。例えば子に120万円を贈与した場合、110万円を超えた10万円分について贈与税率10%がかかり1万円の贈与税が生じます。この程度の税額であっても必ず申告書を提出しましょう。申告漏れがあるとペナルティの対象となり得ます。専門家から見ると、せっかく節税のために贈与したのに申告を怠って余計な税加算を受けるのは非常にもったいないので、ここは注意が必要です。
定期贈与と見なされないように
毎年同じ時期に同額を贈与していると、税務上「最初から複数年分まとめて贈与する約束をしていたのでは?」と疑われるケースがあります。いわゆる定期贈与と判断されると、数年分をまとめた贈与と見做され贈与税を課されてしまう恐れもあります。これを避けるため、契約書上も「今後毎年○万円ずつ贈与する」などとは決して書かず、あくまでその年ごとの単発の贈与であることを明確にしましょう。贈与のタイミングや金額も多少ばらつきを持たせるなど、機械的になりすぎない工夫が望ましいです。
相続時精算課税制度の活用(大きな額を一度に贈与)
暦年贈与では毎年少しずつしか財産を移せませんが、もう一つの制度である「相続時精算課税制度」を使えば、一度に大きな額を子や孫に贈与することが可能です。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、原則として贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上(※成人年齢引下げにより2022年4月以降18歳)かつ推定相続人である子または孫の場合に利用できる制度です。
最大の特徴は、累計2,500万円までの贈与であれば贈与税が一切かからない点にあります。2,500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税を選択すると
相続時精算課税を選択すると、贈与時には大きな額を無税(または定率20%)で渡せますが、その代わり贈与した財産を将来相続税の計算に持ち戻して精算する仕組みになっています。具体的には、この制度で贈与された財産は、贈与者(親)が亡くなった時にその価額が相続財産に加算され、そこから相続税が計算されます。したがって最終的な税負担としては、「生前に一度贈与税で清算する代わりに相続時には課税しない」暦年贈与とは異なり、「生前は贈与税ゼロ(または低率)だが相続時にまとめて課税される」というイメージになります。言い換えれば、相続時精算課税制度自体は相続税そのものを節税する効果はあまりなく、将来の相続税を前倒しで払う(または一部先送りする)制度と言えます。では何のために使うかというと、「子や孫にまとまった財産を早く渡してあげたい」「事業用資産や自宅などを生前に移転しておきたい」といったニーズに応えるための制度と位置付けられています。
相続時精算課税のメリット
最大2,500万円まで無税で贈与できる
一度に住宅購入資金や事業資金など大口の援助をしたい場合、暦年贈与では何年もかけないと渡せない額でも、この制度ならすぐに渡せます。例えば子が家を買う際に親が2,000万円援助するといったケースで、この制度を利用すれば贈与税はかかりません(贈与税の特別控除として2,000万円を適用)。
贈与時の納税負担が軽い
2,500万円を超えた部分についても一律20%の贈与税なので、例えば3,000万円贈与しても超過500万円に対して20%=100万円の贈与税で済みます。本来暦年課税で3,000万円を一度に贈与すると最高55%の税率区分となり贈与税が1,355万円にもなりますから、それと比べるとかなり軽減されます(ただしこの贈与税は相続時に精算されるため先払いに過ぎません)。
相続時精算課税のデメリット・注意点:
相続税の節税効果は限定的
前述の通り、この制度で贈与した財産は結局相続税の計算に含まれるため、相続税自体を減らす効果は基本的にありません。極端に言えば、親の財産が最終的に基礎控除内に収まる見込みであれば節税になりますが、そうでなければ「税金の前払い・繰延べ」をしているだけの側面があります。したがって純粋な節税策というよりは資金移転策と考えるべきです。
適用漏れ(申請漏れ)に要注意
相続時精算課税を使うには、贈与税の申告時に「相続時精算課税選択届出書」を提出して適用を受ける必要があります。一度でもこの届出を忘れると、その贈与は自動的に通常の暦年贈与として扱われ、本来0円で済むはずだった贈与に高額な贈与税が課される事態にもなりかねません。例えば親から2,000万円を贈与した際に届出を失念すると、先述のとおり本来贈与税0円のところが数百万円の贈与税負担となってしまいます。専門家から見ても、この届出書の提出漏れは最も避けるべきミスですので、必ず初回贈与の申告時に提出しましょう。
毎年の申告と記録管理が必要
暦年贈与では110万円以下なら申告不要でしたが、相続時精算課税を利用している間は贈与額にかかわらず年間110万円を超える贈与をした年は毎年贈与税の申告が必要です(110万円以下しか贈与しなかった年は申告省略可)。たとえ贈与税がゼロでも、申告書を出さなければ累計額の管理ができず特例の適用を受けられなくなるので注意しましょう。また、どの財産をいくら贈与したか記録をしっかり残し、相続時に正確に申告できるよう備えておく必要があります。
制度改正(年110万円以下の贈与は“非課税扱い”となり、相続時に持ち戻し不要)により選択の自由度が広がったとはいえ、相続時精算課税制度の利用には慎重な判断が求められます。
大田区の事例でも、親の財産額がそれほど大きくなく子への生前贈与で基礎控除内に収められる見込みであれば有効ですが、そうでない場合は無理に使わず、まず暦年贈与から始めて様子を見るのも良いでしょう。適用を迷う場合は税理士にシミュレーションを依頼し、どちらが有利か試算してもらうことをおすすめします。
生命保険の非課税枠活用や不動産活用による節税
生前にできる相続税対策として、生命保険の非課税枠を活用する方法や現金を不動産に組み換えて評価額を下げる方法も有力です。詳細は別記事「生命保険や不動産活用は相続税対策になる?その他の節税策と注意点」で解説していますが、ここでも簡単に触れておきます。
生命保険の活用
被相続人を契約者・被保険者とし相続人を受取人にした生命保険に加入しておけば、死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは非課税で受け取れます。たとえば法定相続人が子2人なら合計1,000万円まで非課税になり、現金で残すより有利です。また、契約形態を工夫し子どもが保険料を負担する形にすると、保険金は相続税ではなく所得税(一時所得)扱いとなり、50万円の特別控除や1/2課税のメリットで結果的に税負担を軽減できる場合もあります。生命保険は相続税対策と同時に「すぐに現金が入るから納税資金に充てやすい」という利点もあるため、対策として検討の価値があります。
不動産への資産組み換え
現預金をそのまま遺すより、不動産を取得して遺した方が相続税評価額を抑えられる場合があります。土地の評価額は公示地価の80%程度の路線価で計算されるのが一般的で、市場価格より低めになります。建物も固定資産税評価額等で計算され、新築直後でも建築費ベースの評価となるため、現金を投じた額より低く評価される効果が期待できます。さらに賃貸用不動産にすれば、「貸家建付地」の評価減(更地評価の20%減)や「貸家」の評価減(自用建物比で30%減)が適用され、実質的に評価額が半分以下になるケースもあります。例えば1億円でアパートを新築し他人に貸した場合、建物・土地とも賃貸評価減が効いて評価額が時価の約半分程度に圧縮され、そこから借入金があれば差し引いて課税価格を大幅に減少させることが可能です。
これらの手法は有効だが注意が必要
これらの手法は非常に有効ですが、一方で注意すべきポイントも多々あります。
生命保険は非課税枠を最大限活用するには受取人(法定相続人)の人数設定が重要ですし、保険料負担者を誰にするかで税金の種類が変わるなど複雑な面があります。
不動産への組み換えは、物件取得にコストがかかること、売却まで時間がかかり流動性が低下することに注意が必要です。賃貸経営には空室リスクや維持費も伴い、収支が悪化すると本末転倒(節税のために肝心の財産が目減り)になりかねません。特に借入を利用する場合、金利負担と賃料収入のバランスが取れないと残された家族に借金だけが残る結果にもなり得ます。
専門家としても、節税効果とリスクを総合的に判断し、「多少相続税が発生しても親の老後資金は潤沢に残しておく」「不動産は緊急時に売却しづらいので持ちすぎない」といったバランス感覚を持つよう助言するでしょう。
対策の第一歩:資産の棚卸しと専門家への相談
まずは現状を知ること
具体的な方法は色々ありますが、相続税対策の第一歩は何と言っても「現状を知ること」です。まず親御さんの資産・負債を洗い出し、概算で構いませんので自分の家庭は相続税がかかりそうか否かをチェックしてみましょう。国税庁のウェブサイトには「相続税の申告要否判定コーナー」という簡易計算ツールも公開されています。項目に沿って金額を入力すると、相続税申告の要不要をおおまかに判定できますので活用してみると良いでしょう。
専門家への相談も検討
また、資産状況の把握と並行して専門家への相談もぜひ検討してください。相続・贈与に詳しい税理士であれば、各家庭の事情に合わせた最適な対策プランを提案してくれます。税理士の実務経験から言えるのは、「もっと早く相談に来てくれていれば、より選択肢が広がったのに」というケースが少なくないということです。
例えば親御さんが高齢で認知症になってしまうと、生前贈与が難しくなり有効な対策が打てなくなります。そうなる前に手を打つことが重要です。
大田区家族信託・相続相談所でも、相続税対策や生前対策について専門家への無料相談を行っています。思い立ったが吉日、現状で相続税がかかりそうかどうか分からない段階でも構いませんので、お気軽に相談窓口を利用してみてください。対策は早めに始めるほど効果が大きく、結果的にご家族の安心にもつながります。
相続税のご相談は大田区家族信託・相続の相談所へ
相続税対策の基本と、生前のうちに早めに始めたい節税対策のポイントについて解説しました。大田区家族信託・相続の相談所では、相続税や生前贈与を含む生前対策に関する無料相談を承っております。「うちも相続税がかかるかもしれないけれど何から手を付ければ…」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。税理士をはじめ相続の専門家が、大田区の皆様の事情に合わせて最適なプランをご提案し、大切な資産を守るお手伝いをいたします。