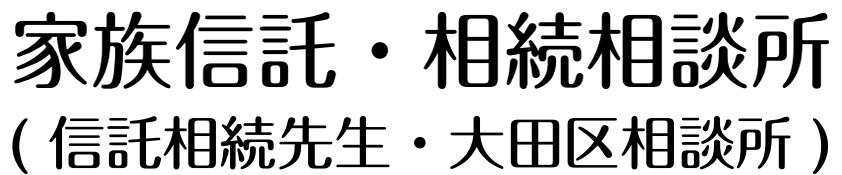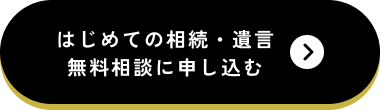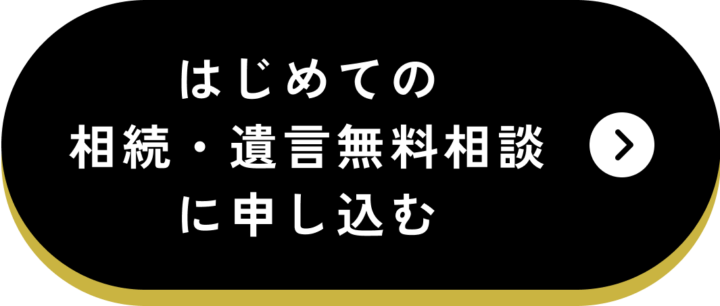未登記借地権信託の法的課題と対策
- 公開日:
- 更新日:
未登記借地権を信託することは可能か?
「未登記の借地権を家族信託に組み入れることはできるのか?」
不動産を家族信託(民事信託)の財産に加えるケースは増えていますが、その不動産が借地上に建っている場合、土地の利用権たる借地権も併せて信託財産にしなければなりません。借地権が登記されていれば信託登記を付すことも検討できますが、現実には借地権が未登記であることがほとんどです。このような未登記借地権を信託財産とする際には、第三者対抗要件や信託法上の公示義務、さらには地主の承諾取得といった幾つもの課題をクリアする必要があります。
適切な対応策を講じないまま信託を組成してしまうと、信託後に借地権を第三者に対抗できず権利保全に失敗するリスクや、受託者が分別管理義務違反など信託法上の義務を果たしていないと評価される恐れがあります。本稿では、未登記借地権を家族信託する場合に押さえておくべき法的課題を整理し、それぞれに対する具体的な対応策を解説します。借地借家法10条・民法612条・信託法14条・34条など関連条文を踏まえ、安全かつ円滑に借地権を信託で承継・管理するための実務ポイントを示します。
未登記借地権が抱える法的課題
未登記借地権を信託財産とする際に問題となる主な法的論点は、次の3点に集約できます。
- 第三者対抗要件の問題(借地借家法10条): 借地権を新たな地主や利害関係人に主張するには対抗要件が必要ですが、借地権自体に登記がない場合の扱い。
- 信託財産の対抗要件の問題(信託法14条): 本来登記が必要な権利を信託財産に移す際、信託登記をしなければ第三者に信託財産性を対抗できないという規定を未登記借地権にどう適用するか。
- 譲渡に伴う地主承諾の問題(民法612条): 借地権(賃借権)の譲渡には地主の承諾が要るため、信託による受託者への地位移転も承諾を得る必要があること。
以下、それぞれの論点を詳しく見ていき、問題点を整理します。
借地借家法10条:建物登記による借地権の対抗力
借地借家法10条は、借地権の第三者対抗要件についての特則を定めています。同条1項によれば、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者名義で登記された建物を所有している場合には、第三者に対抗できる」と規定されています。つまり、借地権者が当該土地上の建物を自己名義で登記している限り、土地賃借権そのものに登記がなくても、新しい地主や抵当権者など第三者に借地権を主張できるということです。
この規定により、借地契約実務では建物の登記が借地権の対抗力を担保する形が一般的です。多くの借地権は登記されていませんが、借地上の建物登記名義が借地人であることによって第三者対抗要件を充足させています。したがって、未登記借地権であっても借地人が建物を所有・登記している限り、現状では権利行使に大きな問題は生じません。
しかし、家族信託の場面では注意が必要です。信託によって借地権者の地位が委託者から受託者に移ると、借地借家法10条の要件を満たすためには建物の登記名義も受託者に変更しなければなりません。もし信託設定後も建物名義が委託者のままだと、受託者(新たな借地権者)は「土地上の登記建物を所有」していないことになり、借地権の対抗力が失われてしまう恐れがあります。さらに、建物自体が老朽化等で滅失してしまった場合は、原則として借地権の対抗力は消滅します。借地借家法10条2項により滅失後2年間は掲示により対抗力を維持できますが、長期間建物がない状態が続けば権利主張が危うくなります。
このように、未登記借地権の信託では建物登記の扱いが極めて重要であり、信託時に受託者へ確実に建物名義を移転すること、さらには信託期間中も建物の存在と登記名義の維持に留意することが必要です。
信託法14条:信託登記が要求される財産と未登記借地権
信託法14条は、「登記しなければ権利変動を第三者に対抗できない財産」については信託による移転でも信託登記等をしなければ信託財産として主張できないとする規定です。典型的には不動産や自動車など登記制度が整備された財産が該当します。
一方、土地賃借権(借地権)のように本来登記を要しない債権的権利は、この「登記をしなければ対抗できない財産」に当たるかが問題となります。借地権については借地借家法10条で特則があり、建物登記で対抗力を得られる仕組みです。したがって、否定的な見解では「借地権は既に特別の対抗要件制度があるのだから、信託法14条の適用対象ではない」と解釈します。つまり、未登記借地権を信託しても、建物登記という既存の対抗手段がある以上、改めて信託登記を要求されないという考え方です。
一方で肯定的な見解では、「借地権も不動産利用権であり、所有権に準じて扱うべきだ」として、信託による地位移転時にも何らかの登記的公示がなければ第三者対抗できないのではないか、と指摘します。実際、信託財産であることを主張できないと、受託者の債権者がその借地権に対し差押えなどの強制執行をしてきた場合に、防御が困難になる可能性があります。
現行法上、借地権の設定登記が前提として存在しない限り、借地権そのものに信託登記を付すことはできません。よって、肯定説に立つと「未登記借地権の信託は常に第三者に対抗できないリスクがつきまとう」という結論になりかねません。この問題に明確な結論は出ていませんが、万全を期すなら肯定説を念頭に置いた対応策を講じる必要があります。具体的には、信託法14条の要請に応える形で、借地権が信託財産であることを他から見ても分かるようにする措置を取ることです。これは後述の分別管理義務(信託法34条)の話題とも深く関わります。
地主の承諾と譲渡禁止特約(民法612条・借地借家法19条)
借地権(特に賃借権)の譲渡には地主の承諾が必要です(民法612条1項)。家族信託による借地権の受託者への移転は法律上「譲渡」とみなされるため、地主の事前承諾を得なければ契約違反となります。承諾を得ずに譲渡した場合、地主は契約を解除できるとされています(民法612条2項)。これは家族間の信託であっても例外ではなく、借地契約上の譲渡禁止特約も当然に適用されます。
したがって、未登記借地権を信託する際には地主への説明と承諾取り付けが不可欠です。加えて、承諾に際して地主から承諾料(名義書換料)を請求されることが一般的です。その相場は借地権評価額の約10%といわれますが、家族内承継で利用状況が変わらないことを説明することで減額や免除を引き出せる余地もあります。
もし地主がどうしても承諾しない場合には、借地借家法19条の裁判所許可の制度を利用することになります。これは「借地上の建物を第三者に譲渡する場合」に借地人が申立てを行い、正当な理由なく承諾しない地主に代わって裁判所が許可を与える手続です。家族信託で受託者に建物と借地権を移すケースも、この「建物譲渡を伴う借地権譲渡」に該当するため、条件を満たせば許可が下りる余地があります。ただし裁判所手続には時間とコストがかかるため、現実には地主を丁寧に説得して任意に承諾を得るルートを模索すべきです。
以上のように、未登記借地権の信託には(1)借地借家法10条の対抗要件維持、(2)信託法14条の解釈上のリスク、(3)地主承諾取得と承諾料という課題が横たわります。では、これらに対してどのような実務対応策を講じればよいのでしょうか。次章で具体的なポイントを説明します。
未登記借地権を信託財産とするための主要な対応策
上記の課題を踏まえ、未登記借地権付き物件の家族信託では次のような対応策を総合的に講じることが重要です。
建物の受託者名義への変更と信託登記の実施
借地上の建物を信託財産に含め、受託者への所有権移転登記を行います。さらに登記簿に信託の旨を記載(信託登記)しておくことで、受託者が新たな借地権者であり当該建物・借地権が信託目的に属することを公示します。これにより、借地借家法10条の対抗要件(受託者名義の建物登記)が満たされ、借地権の対抗力が維持されます。また、信託目録に底地に関する借地権も信託財産であると明記し、権利関係を明らかにしておきます。
信託契約書の公正証書化
信託契約は可能なら公証人役場で公正証書として作成します。公正証書にしておけば、契約の成立日時や内容(未登記借地権も信託財産に含まれること)が公的に証明され、受託者の倒産時などに「その借地権は信託財産である」という主張を裏付ける強力な証拠となります。特に未登記権利を扱う以上、契約の日付確定と内容証明の効果が得られる公正証書化は安全策として有効です。
受託者による分別管理の徹底
信託法34条に基づき、受託者は信託財産と固有財産を厳格に分けて管理します。具体的には信託専用の預金口座を設けて借地権に関する収支(金銭)を管理し、信託財産専用の帳簿を作成して経理します。こうした分別管理の実践により、受託者の他財産と借地権関連財産の混同を防ぎ、第三者から見ても当該資産が信託財産であることを明確化できます。結果的に、信託法14条の趣旨に沿った公示効果と信託法34条の義務履行を果たすことにつながります。
地主からの承諾取得と適切な承諾書の整備
信託契約を締結する前に地主の承諾を文書で取得します。承諾書には、借地権および借地上建物を信託により受託者へ譲渡することを地主が承諾する旨を明記し、信託期間中の受託者変更や信託終了時の名義復帰も包括して許可する文言を盛り込みます。さらに、信託後も土地賃貸借契約の条件は一切変更されないこと、元借地人である受益者が引き続き建物を使用することを承諾する旨など、地主にとって不利益や不安がないことを確認する条項を入れます。こうした借地権譲渡承諾書を交わしておけば、現地主にはもちろん、将来地主が交代しても承諾の効力を主張しやすくなります(承諾書は契約の一部として新地主にも引き継がれます)。承諾料についても、交渉結果を踏まえて金額や支払い時期を明記します。
裁判所許可制度の検討(必要時)
地主の承諾がどうしても得られない場合や承諾料の折り合いがつかない場合、借地非訟手続による裁判所許可を視野に入れます。もっとも、この手続は最後の手段であり、専門家としては可能な限り地主との事前調整で解決を図るべきです。許可を得る場合でも、裁判所から承諾料相当額の供託や地代の増額など条件が付されることがあります。
以上の対策を組み合わせることで、未登記借地権を含む家族信託でも実務上のリスクを大きく低減できます。次項では、これらのポイントについてさらに具体的な実務上の留意点を補足します。
実務上の留意点
建物の信託登記と借地権の対抗力維持
家族信託では委託者から受託者へ不動産の所有権を移転するため、借地上の建物も受託者名義に登記し直します。同時に信託目録を作成して信託の内容を登記簿に公示します。この手続きを怠ると、受託者が借地権者となったにもかかわらず登記上は建物所有者でない状態となり、借地権の対抗要件を喪失します。信託登記は法的義務であると同時に借地権対抗力維持の生命線です。登録免許税等の費用負担はありますが、必要経費と割り切って必ず実行しましょう。
信託目録への記載については、上記の通り借地権も信託財産だと読み取れるよう工夫します。利害関係人が登記簿を閲覧したとき「この建物は信託されており、その底地借地権も信託財産なのだな」と分かる状態にしておけば、後々の紛争予防につながります。ただし、信託内容を詳細に公開しすぎるとプライバシーの問題もあるため、記載内容は必要最小限に留めつつ肝心な点(借地権も信託財産である旨)は明示するバランスが求められます。
信託法14条への対応と分別管理
未登記借地権の場合、厳密には信託法14条の対抗要件を充足できない可能性が残ります。この点は割り切りが必要で、当面の実務では信託法34条の分別管理義務を徹底することが唯一の対応策と言えます。具体的には前述の通り、書面や帳簿、口座管理などソフト面で「これは信託財産だ」と分かる状況を作り出すことです。
例えば受託者個人の預金と信託預金が混在していなければ、差押えに対しても「この預金は信託専用口座で管理されており信託財産です」と主張しやすくなります。また、受託者の他財産と区別して管理している事実があれば、万一第三者との紛争になっても信託財産であることの間接的証拠となります。受託者の忠実義務・善管注意義務の観点からも、分別管理を尽くしていれば信託財産保護のため最善を尽くしたと評価されるでしょう。
地主交渉のコツと承諾書管理
地主への説明は、専門用語を避け平易に行うことがポイントです。家族信託=家族による財産管理の一環であって、使用実態や契約条件は何ら変わらないことを強調します。「名義が息子に変わるだけで、これまで通り私(親)が住み続け、地代も確実に払います」という説明をすれば、大半の地主は安心します。承諾料についても「できればご配慮いただきたい」と相談し、減額の余地を探ります。信託であれば承諾料は不要とする事例、ハンコ代程度の金額にしてもらえたという実例もあります。
承諾書は一度交わせば終わりではなく、将来にわたって重要な証拠として保管・活用します。地主が代替わりした場合、新地主に早めに承諾書の存在を知らせ、理解を得ておくと良いでしょう。承諾書の原本は受託者または専門家が厳重に保管し、必要に応じてコピーを関係者と共有します。
信託スキーム全体の見直し
借地権を信託財産に組み込むことに過度なコスト(承諾料など)やリスクが伴う場合、別の財産承継手段も検討に値します。例えば親子間で借地権を引き継ぐだけなら、親から子への生前贈与や遺言による相続でも形式的には実現できます。ただし、贈与は贈与税や不動産取得税の問題に加え、親の財産ではなくなるという問題、遺言では、親の認知症などによる資産凍結対策とならないという問題があります。
家族信託では、こうした問題が生じないため、トータルで考えて信託を選択する意義は高いです。その場合には、本稿で述べた対策を講じてリスク低減に努めることになります。
なお、どうしても地主が承諾料を譲らず負担が難しい場合、信託ではなく任意後見契約やその他の方法で対応することも検討する必要があるでしょう。
まとめ:未登記借地権信託のポイントと展望
未登記借地権を信託財産にする家族信託は、一見ハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、本稿で述べたように適切な法的対応策を講じれば実現可能です。要点を振り返りますと:
- 借地借家法10条の特則により、借地権は建物登記で第三者に対抗可能なので、信託後は受託者名義で建物登記を維持することが重要です。
- 信託法14条の解釈上の不安に対しては、信託登記ができない分、他の手段で信託財産であることを明確化します(信託目録への記載、帳簿管理、口座分別等)。
- 分別管理義務(信託法34条)を忠実に履行し、受託者の固有財産と信託財産を厳格に分離して管理することで、信託財産の保全と対抗力維持に努めます。
- 地主の承諾取得は不可欠であり、丁寧な交渉と合意内容を盛り込んだ承諾書の作成が肝要です。承諾料はケースバイケースですが、家族信託の趣旨を理解してもらうことで柔軟な対応が期待できます。
- 信託契約は公正証書化しておく、承諾書は厳重に保管するなど、将来の紛争に備えた証拠化も忘れてはなりません。
借地権という権利は確かに特殊で難解ですが、近年は高齢化に伴う認知症対策や相続対策として家族信託で借地権を承継・管理したいというニーズも増えています。まだ判例や実務指針が十分に確立されていない分野ではありますが、専門家が創意工夫して安全なスキームを構築していく余地があります。借地借家法や信託法の制度趣旨を正しく理解し、関係当事者に寄り添った丁寧な対応をすることで、未登記借地権の信託活用も決して不可能ではありません。本稿の内容が、現場で検討・実践される際の指針となれば幸いです。