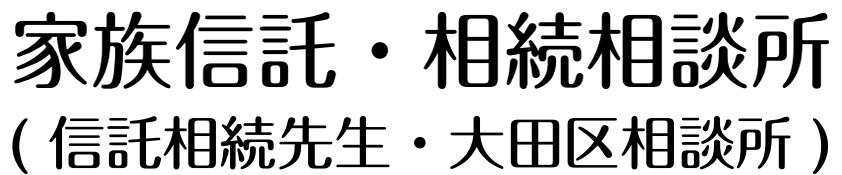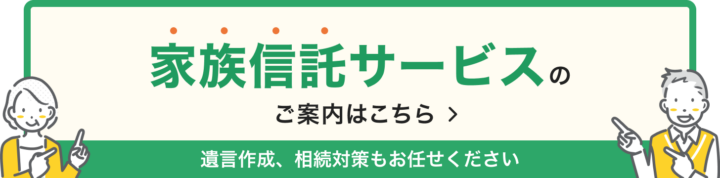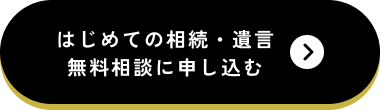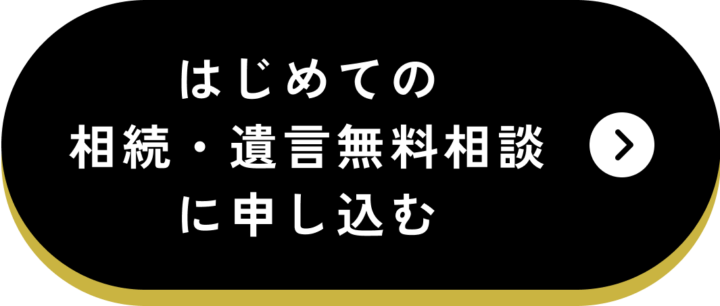家族信託のメリット・デメリットとは?利用前に知っておきたいポイント
- 公開日:
- 更新日:
大田区で高齢の親族を抱えるご家庭から「家族信託の利点と欠点を知りたい」という相談が増えています。家族信託(民事信託)とは、親など委託者の財産管理を信頼できる家族(受託者)に任せる制度です。認知症対策や相続の円滑化に役立つ一方、手続き面の注意も必要です。ここでは、司法書士の専門家視点から家族信託の主なメリットとデメリットを解説し、利用前に知っておきたいポイントを大田区の地域事情も交えて紹介します。高齢化率約22%と高い大田区でも、家族信託への関心が高まっています。良い面だけでなく懸念点もしっかり理解し、ご自身の状況に家族信託が適しているか判断する材料にしてください。
家族信託の主なメリット
家族信託には柔軟な契約内容や幅広い対応範囲による多くのメリットがあります。特に次のような点が大きな利点です。
認知症による資産凍結を防げる(柔軟な財産管理)
親が認知症を発症した場合、通常は銀行口座が凍結され、家族でも親の預金を引き出せなくなるリスクがあります。しかし家族信託を活用すれば、親の判断能力が低下しても、受託者である子どもが契約内容に従って財産管理・処分を続けられます。例えば大田区内の事例でも、信託後に親が施設入所となっても生活費や医療費の支払いを子どもが滞りなく行えたケースがあります。家族信託により銀行口座の凍結や法律行為の制限を回避でき、認知症による資産凍結を防止して家族の負担を軽減できるのが大きなメリットです。
遺言書にはない機能(遺産承継の柔軟な指定が可能)
家族信託は遺言代用の仕組みとしても機能します。通常、遺言書では自分の死亡後の財産分配を一度きりしか指定できません。
しかし家族信託なら、複数世代にわたる承継先をあらかじめ決めておくことができます。
例えば「父から母、その後長男へ」と二次相続まで受益者を指定しておくことが可能です。遺言では本人死亡までしか効力が及びませんが、信託契約なら親の存命中から死亡後、その次の世代まで柔軟に財産承継の順序を定めることができます。これにより、二次相続対策や複雑な家族構成における遺産承継にも効果的です。
実際に「親の再婚後の家庭で、先妻の子と後妻の間の相続紛争を避けるため信託を活用した」ケースもあります。家族信託なら当事者全員が元気なうちに話し合った分配方法を契約に盛り込めるため、後の遺産分割トラブルを予防できます。
家庭裁判所を介さず家族で資産管理ができる(成年後見制度より柔軟)
判断能力が低下した親の財産管理には成年後見制度という公的制度もあります。しかし成年後見では家庭裁判所による管理監督や後見人への報告義務が課され、さらに後見人(専門職後見人が選ばれる場合も多い)は被後見人本人に利益があること以外できないため、家族のための出費や資産運用の柔軟性が制限されがちです。
例えば後見人が付くと、それまで親が援助していた家族旅行の費用負担なども「本人の利益にならない」と制限されてしまうケースがあります。一方、家族信託では信頼できる親族を受託者に指名でき、契約で定めた親の意思や希望に沿って資産を活用できます。後見のような煩雑な報告や監督も不要で、必要に応じて遊休不動産の売却・建替えなど積極的な資産活用も可能です。
つまり家庭裁判所を介さずに済み、親族が主体的・柔軟に財産管理できる点も家族信託のメリットと言えます。
家族信託の主なデメリット
一方で、家族信託を利用する際には以下のようなデメリットや注意点も押さえておく必要があります。
手続きの複雑さと費用負担(契約書作成や登記費用など)
家族信託の設定には専門的な手続きとコストが伴います。信託契約書の作成には法律知識が不可欠で、不動産を信託すれば登記変更も必要です。そのため実務上は司法書士や弁護士など専門家のサポートがほぼ必須であり、依頼する場合は報酬や手数料といった費用が発生します。例えば信託コンサルティング設計費用が20~30万円、契約書作成費用が約30万円、公正証書化に7~10万円程度など、初期費用だけで数十万円になるケースもあります。また不動産を登記する際は評価額の0.3~0.4%の登録免許税が課税され、物件ごとに司法書士への手続報酬(1物件あたり数万円)がかかります。このように家族信託は設定時にまとまった費用負担が生じ、手続きも煩雑なため準備に時間と労力を要する点はデメリットです。ただし一度信託を組成してしまえば、成年後見人のように毎月の報酬が継続してかかることはなく、維持費用は比較的抑えられるメリットもあります。
信託財産の管理責任・手間がかかる
家族信託では財産の管理・運用責任が受託者(託された家族)に集中します。受託者は信託契約に沿って資産を適切に管理しなければならず、その責任と事務負担は決して軽くありません。
例えば複数の不動産や金融資産を信託すれば、賃貸管理や売買判断、税金の支払いなど日常的な手続きが発生します。受託者が忙しかったり管理能力に不安がある場合、信託の運用が滞ったり財産価値が目減りするリスクもあります。また家族間とはいえ金銭管理を代理で行うため、他の相続人から不信感を抱かれないよう透明性のある運用(定期的な収支報告等)も求められます。信託監督人や第三者の専門家を関与させることもできますが、その場合はさらに費用がかかります。家族信託を成功させるには、適任の受託者選びと事前の十分な合意形成が不可欠です。
実際、家族信託の専門知識や経験を持つ士業者はまだ多くないため、信頼できる専門家の助言を受けつつ適切な受託者を選定することが重要でしょう。
家族内の理解不足によるトラブルの可能性
家族信託は家族間の信頼と協力が前提の制度です。もし他の家族が信託内容を理解・納得していないと、後になって「受託者が独り占めしているのでは」など不信や争いの火種になる恐れがあります。特に遺産分割の代替機能を持つため、信託設定時に関与しなかった親族が後から異議を唱えるケースも考えられます。家族内トラブルを防ぐには、契約前に関係者全員で十分に話し合い、信託の目的や分配ルールについて共通理解を持っておくことが大切です。また契約後も、節目ごとに受託者から収支状況を共有するなど透明性ある運営に努めると安心です。専門家の立会いのもと家族会議を開き、合意内容を正式に文書化して信託契約に反映させることで、「聞いていない」「そんなつもりではなかった」といった行き違いによる紛争を予防できます。
税制面での節税効果は限定的
家族信託は主に財産管理や承継方法の柔軟性にメリットがある制度であり、相続税の節税対策が目的ではありません。信託したからといって相続税評価額が下がるわけではなく、基本的には従来どおり課税対象となります。
また信託開始時に子へ財産を移す形態によっては贈与税の問題も生じ得ます(一般に委託者=受益者の形で信託すれば贈与税は非課税です)。
近年の税制改正で、生前贈与の扱いが変わった点にも注意が必要です。2024年以降、死亡前7年以内の贈与財産は相続財産に持ち戻して課税されるルールに段階的に延長されました(従来は3年以内)。そのため、生前に多額の財産を移して相続税を減らす効果は限定的になっています。
一方、相続時精算課税制度には2024年より年間110万円までの非課税枠が新設され、毎年110万円までは相続財産に加算されない措置も導入されました。
これにより贈与税と相続税を一体で考える制度の使い勝手は向上しましたが、家族信託自体が節税になるわけではない点は理解しておきましょう。「信託=節税」と誤解していると期待外れに終わる可能性があるため、税務面の効果は専門家に確認しつつ冷静に判断してください。
家族信託が向いているケース・向かないケース
以上のメリット・デメリットを踏まえ、家族信託の利用が特に有効なケースと、逆に他の手段の方が適しているケースを整理します。ご自身の状況と照らし合わせる参考にしてください。
向いているケース:親が認知症になる前に備えたい場合
将来的に親の判断能力低下が心配で、財産凍結への備えを早めに講じておきたい場合、家族信託は有力な選択肢です。例えば「最近物忘れが増えた親の預金管理を子に任せ、万一に備えたい」というケースでは、親が元気なうちに信託契約を結ぶことで、認知症発症後もスムーズに財産管理が継続できます。成年後見制度では発症後に手続きを開始するため、タイムラグや制約が生じますが、家族信託なら事前対策が可能です。認知症リスクに不安を感じているご家庭には特に向いている制度と言えるでしょう。
向いているケース:複数の不動産など資産があり管理を任せたい場合
親御さんが複数の不動産や事業用資産、金融資産を所有している場合、それらを一元管理する手段として家族信託は効果的です。例えば大田区内でも土地・建物を複数所有し賃貸経営をしている高齢オーナーの方が、息子を受託者として信託契約を結び資産管理を任せるケースがあります。こうした契約により、不動産の賃貸運営や売却・建替えの判断を子に託し、資産管理の効率化と継続性を図れます。親が高齢になると煩雑な資産管理は負担となりますが、信託によって頼れる家族にバトンタッチすることで、本人の生活を支えつつ資産価値を維持・向上させることが可能です。収益不動産の管理・承継を円滑に行いたい場合にも家族信託は適しています
【向かない】不動産保有がない場合
親の財産に不動産や株式がなどがない場合、家族信託の利用しなくても、親の財産管理は可能です。近年、金融機関によっては事前に手続きをしておくことで、家族が本人に代わって預金の引き出しや振込といった処理が可能な制度を用意していることがあります。たとえば「代理人届」や「代理人カード」といったしくみです。手続き名称や手続き内容は金融機関ごとに異なりますが、多くの場合、無償で対応してもらえるのが特徴です。
このような制度を活用すれば、万が一親が認知症になっても一定の範囲で預金の処理が可能となり、最低限の資金管理は対応できることもあります。したがって、事務負担や費用対効果を考えると、「預金凍結のリスクに備える」だけの目的で家族信託を利用することは、強く推奨は致しません。
向かないケース:家族間の信頼関係に不安がある場合
家族信託は家族の絆や信頼が前提となる契約です。もし家族仲が悪かったり、受託者候補に信頼を置けない状況で無理に信託を組むと、かえってトラブルを招きかねません。他の相続人から「受託者が不正をしているのでは」と疑われて争いになる事例も報告されています。特に財産を任せられる適切な人物が見当たらない場合や、親族間に根深い対立がある場合には、家族信託以外の選択肢(遺言+第三者の遺言執行者を指定する、成年後見制度を利用する等)も検討すべきでしょう。
家族信託は強力な仕組みですが人間関係の問題を解決する魔法ではありません。家族内の協調が難しいケースでは無理に活用しない方が賢明です。
まとめ:メリット・デメリットを踏まえた検討を
家族信託には以上のように長所と短所があります。認知症対策や柔軟な資産承継を実現できる反面、手続きの煩雑さや費用、家族間調整の難しさといった課題も存在します。大田区家族信託・相続の相談所では、こうしたメリット・デメリットを丁寧にご説明しながら、それぞれのご家庭に最適な相続対策を一緒に考えております。「自分のケースでは家族信託を利用すべきか?」と迷われたら、まずは専門家に相談し客観的なアドバイスを得ることをおすすめします。メリットとデメリットの双方を正しく理解してこそ、家族信託は安心して活用できる制度です。
家族信託のご相談は大田区家族信託・相続の相談所へ
大田区で家族信託の利用をお考えの方は、ぜひ大田区家族信託・相続の相談所にご相談ください。当相談所では司法書士を中心とした専門家チームが、家族信託のメリット・デメリットについて丁寧にご説明し、お客様の事情に合わせた最適な信託スキームをご提案します。初回の無料相談も実施しておりますので、「我が家の場合は家族信託が良いのか知りたい」「信託契約の手続きを具体的に教えてほしい」といった疑問に専門家が直接お答えいたします。大田区地域の事情に精通した相談所として、地元の皆様が安心して財産管理・相続対策できるよう全力でサポートいたします。家族信託のご検討は、ぜひ当相談所にお気軽にお問い合わせください。